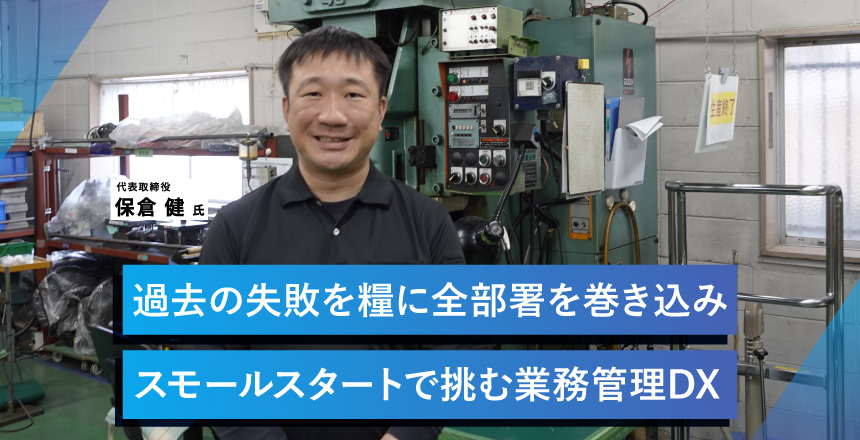2025年から、DXの取り組みに着手
2025年度に大阪DX推進プロジェクトのDX推進コンサルタントの専門家派遣を利用
Q. DX推進に挑戦するきっかけとなった自社課題は。
当社は1936年に創業し、電池パックの組立加工、精密抵抗溶接、プレス加工などを手がけてきました。長年、課題を感じていたのが業務管理で、社内に基幹システムが存在せず、社員が個々に作成したエクセルのフォーマットで日々の業務を管理している状態でした。そのため業務が属人化してしまい、担当者が休むと仕事が止まる、社員の配置転換ができない、などの問題を抱えていました。

高い技術力や作業現場の環境整備といった細部へのこだわりが顧客からの信頼に繋がっている
さらに、材料の管理の複雑さも問題となっていました。当社が扱う電池パックには多くの材料が使われますが、材料の種類によって管理の単位が「個数」「重さ」「長さ」などバラバラです。また、自社購入ではなく取引先からの預かり在庫であることも多く、その受発注管理には高い正確性が求められます。今後の生産性向上を考慮すると、業務管理の効率化は必須の課題でした。
Q. どのようなDX推進を行いましたか。
DX推進コンサルタントの黒﨑さんにアドバイスいただき、まずは社内にプロジェクトチームを組成しました。チームには全部署からメンバーを集めましたが、その背景には過去の苦い経験があります。当社では2年ほど前に高額な費用をかけて基幹システムを導入したものの、活用できずに運用を断念した経緯があります。失敗の原因としては、関係する部署のメンバーだけで進めたことと、いきなり大規模なシステムを導入したことです。そのため今回は全部署の意見を取り入れつつ、スモールスタートで進めることにしました。
チーム組成後は、日々の業務で感じている課題や改善点をリストアップしました。この時、黒﨑さんからは「DX」や「デジタル」に内容を限定せず、業務上の改善点を全般的に洗い出すようアドバイスをいただきました。その結果、200を超える課題が集まり、その中から「受発注管理」の改善を優先的に進めることが社内の意見として一致しました。
Q. DX推進後に経営内容や社内・社員に変化はありましたか。
ちょうど同じ頃、ITの知見を持つ社員が中途入社した経緯もあり、簡易的な受発注管理システムを自社で開発することになりました。まずは1社の顧客に特化したシステムとしてコアメンバーで試験的に運用することで、将来的な本格運用へのステップを模索しています。同時に、システム開発が属人化してしまうのを避けるため、社内の若手人材に開発を引き継ぐための体制を整えています。
Q. 今後どのような展開を検討されていますか。
当社の業務にはまだアナログな作業が多く、例えば製造現場の生産日報も未だに手書きで集計している状況です。いずれはタブレットで入力し、自動集計するようなシステムに変えていきたいと考えています。生産計画も現在は特定の社員に頼っているため自動化する方法を探っており、技術継承に関しても動画を活用したツールの導入を計画しています。
電池パックの組立加工の拠点は多くが海外へ移転し、国内で事業を続けていくには高付加価値化や多品種小ロットへの対応力が求められます。人材不足の中でこれらを実現するためにも、デジタルを活用した生産効率の向上に今後も力を入れていきます。

会社全体に定着した改善意識が、DXを推し進めている
DX推進コンサルタント黒﨑からのコメント
三興工業様のDX推進は、長年の課題であった業務の属人化と非効率な管理体制という、まさに組織の根幹に関わる課題に正面から向き合うことから始まりました。
特に注目すべきは、過去の高額なシステム導入失敗の経験を糧に、今回は全部署を巻き込んだプロジェクトチームを組成し、スモールスタートで変革に挑まれた点です。そして「DX」に限定せず業務上の改善点を全般的に洗い出した結果の中から「受発注管理」の改善を優先的に進めるという社内合意に至ったことは、三興工業様に備わっている「考える組織づくり」と「改善意識の定着」を示す素晴らしい成果です。IT知見を持つ社員によるシステムの内製化と若手への技術継承まで見据えているのは、まさに本質的なDX推進の姿勢であると感銘を受けました。
三興工業様の継続的な挑戦が、国内での高付加価値化や多品種小ロット対応力強化に繋がり、持続的な成長を実現されることを期待しています。

左より保倉氏、DX推進コンサルタント黒﨑氏